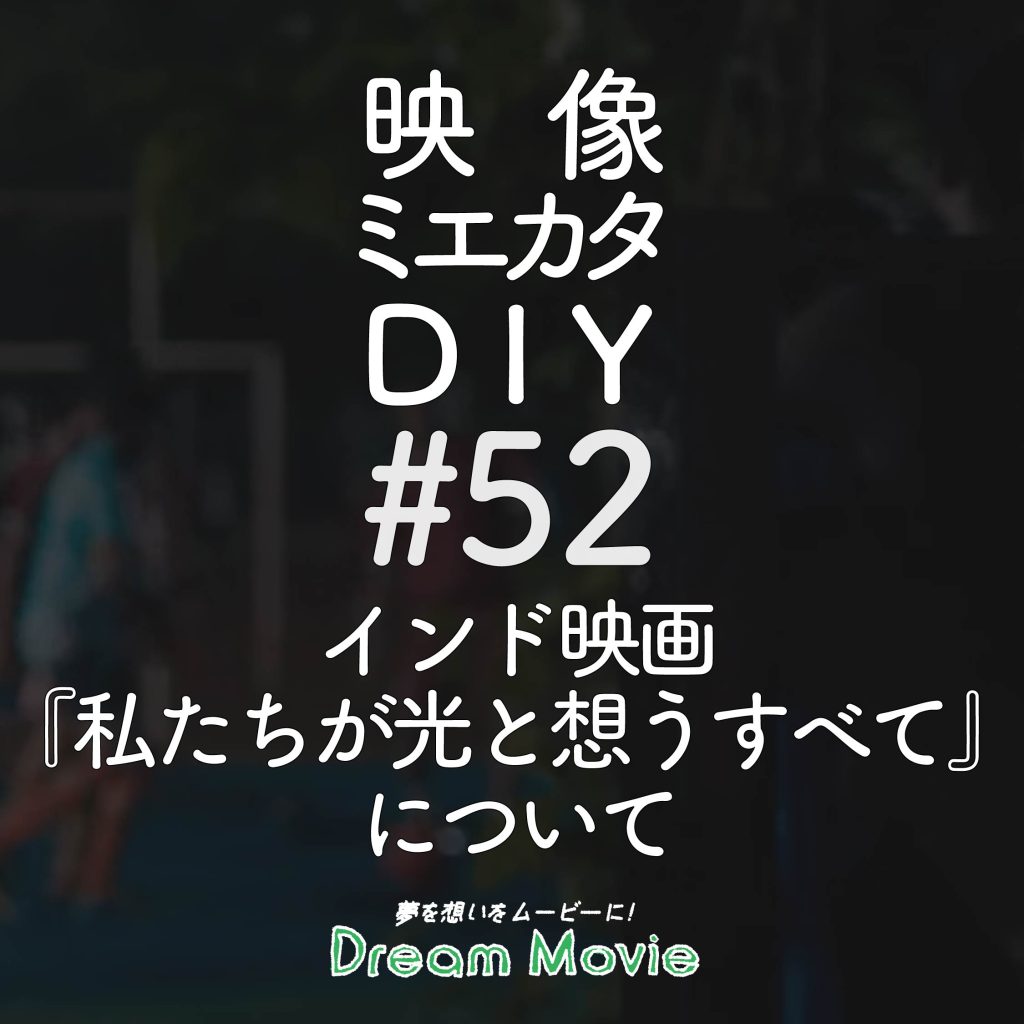
「映像ミエカタDIY」は、当たり前のように受け取っている映像の効果について、身近な素材を取り上げながら改めてその面白さを確認していくシリーズです。今回はインドのムンバイ出身の映画作家、パヤル・カパディアによる長編劇映画デビュー作『私たちが光と想うすべて』について紹介します。
『私たちが光と想うすべて』は「インド映画」として、2024年のカンヌ国際映画祭に30年ぶりにコンペティション部門にノミネートされ、最高賞パルム・ドールに次ぐグランプリを受賞しました。しかし『私たちが光と想うすべて』は私たちが「インド映画」として真っ先に思い浮かべるものとは趣が異なる映画です。
そこにあるのは「ボリウッド映画」の華やかな歌やダンスとは一線を画した、ムンバイの雑踏に暮らす女性たちの日常を詩的かつドキュメンタリー的なリアリズムで捉えた視線です。
いわゆる「インド映画」との距離を考えるときに、ヨーロッパの映画作家からの多くの参照があること、そして製作自体もフランス、インド、オランダ、ルクセンブルクといった国々が製作国として名を連ねている点も注目すべきポイントです。ヨーロッパでの作家性を大切にした若い世代の女性監督が活躍する流れの中で、インド出身の優れた作家にも光が当たったことはとても印象的です。
異なる境遇を生きる3人の女性たちの孤独と連帯
物語の中心となるのは、ムンバイの病院で働く3人の女性、プラバー、アヌ、パルヴァティーです。
看護師のプラバーは、真面目で責任感が強い女性ですが、お見合い結婚をした夫がドイツへ渡ってから1年以上音信不通という孤独を抱えています。彼女は夫への忠誠心と、心に燻る切望の間で揺れ動き、感情を内に秘めて日々を過ごしています。
同僚でルームメイトのアヌは、南部出身の若き看護師。自由奔放でロマンチックな愛を夢見ていますが、恋人であるシアズがイスラム教徒であるため、ヒンドゥー教徒である家族に知られないように秘密の関係を続けなければなりません。彼女の恋愛は、インド社会が抱える宗教的な分断という、デリケートな現実を静かに示唆しているようです。
そして、プラバーとアヌの住むアパートの家主であるパルヴァティーは、夫を亡くした高齢の女性。スラムの撤去により、住居の権利を証明する書類がないため、長年住み慣れた家を失う危機に直面しています。彼女の物語は、ムンバイの急速な都市開発と、それに伴う格差や立ち退きの問題を浮き彫りにしています。
カパディア監督は彼女たちの苦悩を大げさに描くことはしませんが、その代わりに彼女たちが互いに支え合い、小さな瞬間に喜びや安らぎを見出す様子を、温かくそして親密なまなざしで映し出しています。
詩的な映像美、リアリズムと幻想が融合する物語
この映画の最大の魅力の一つは、その映像表現にあります。ドキュメンタリー映画出身である経験が活かされ、ムンバイの雑踏や人々の表情は驚くほどリアルで生々しい一方で、映像は常に詩的な美しさに満ちています。
特に夜のシーンや雨のシーンは幻想的で、ムンバイという大都市の混沌とした活気の中にも、どこかセンチメンタルな感覚を漂わせています。個人的にはシャンタル・アケルマン監督の傑作『アンナの出会い』(1978)を思い出すような美しさを感じました。
映画の終盤、女性たちがムンバイを離れて海辺の村へ旅をする場面では、澄んだ空気と穏やかな光が、彼女たちの内面の解放を象徴するように描かれています。
大都市ムンバイと海辺の村という2つの舞台は、映像的な対比だけではなく、物語る方法の対比としても描かれています。ムンバイでの出来事は厳格なリアリズムとして描かれ、海辺の村でのことはある種幻想的な物語として表現されています。孤独と向き合うために幻想的な出会いを用意するという終盤の演出は、アンドリュー・ヘイ監督作品『異人たち』(2023)を思い出すものでもあり、作品を貫く詩的な映像美が結実するポイントとしても強く印象に残るものでした。
・
『私たちが光と想うすべて』は、ムンバイという特定の土地の物語でありながら、そこで生きる人々の孤独、希望、そして連帯という普遍的なテーマを扱うことで、多くの人の心に深い余韻を残す作品です。日本での公開はまだ始まったばかりです。その詩的な映像表現を映画館の大きなスクリーンでぜひ体験してみてはいかがでしょうか。
劇中の音楽も素晴らしかったです!名曲”The Homeless Wanderer”の使い方がとても印象的でした。(了)
