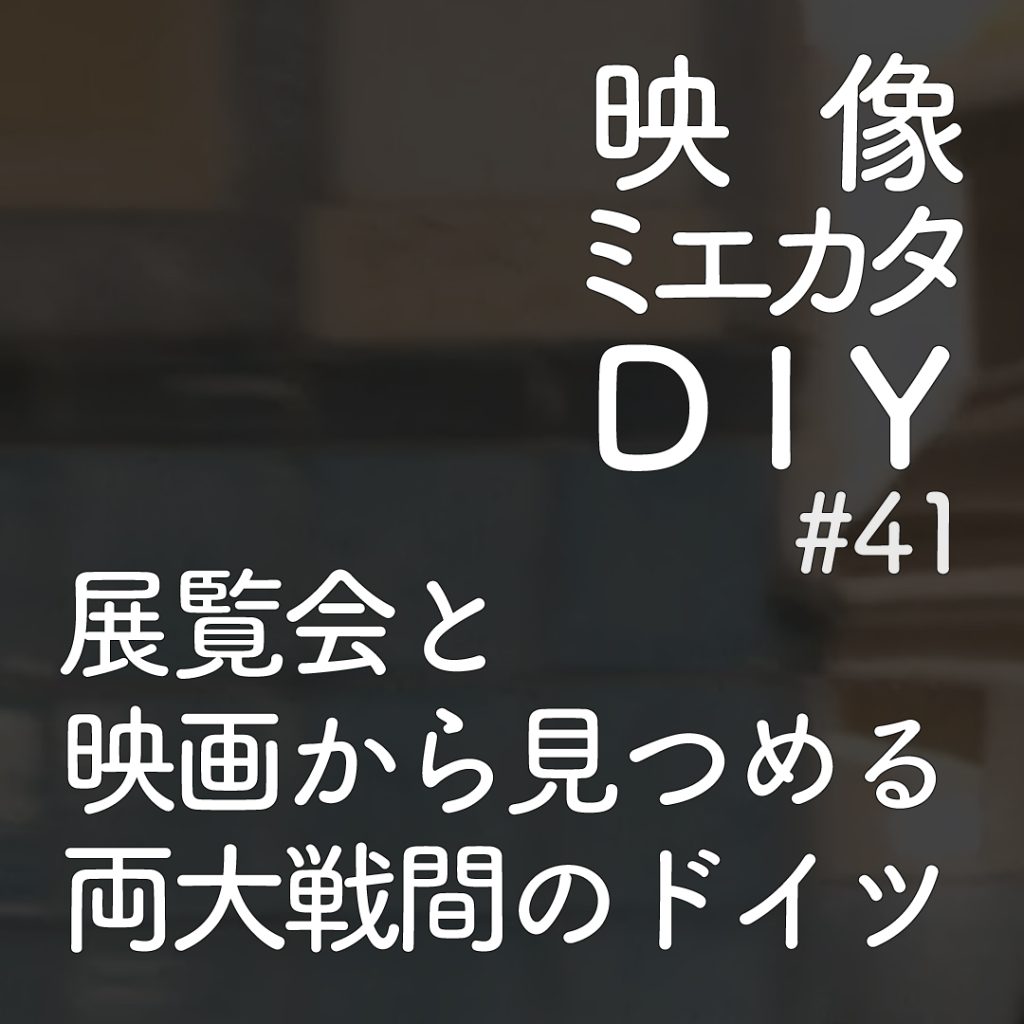
「映像ミエカタDIY」は当たり前のものとして受け取っている映像の効果について、身近な素材を取り上げながら、改めてその面白さを確認していくシリーズです。
今回は両大戦間の版画作品を取り上げた展覧会『両大戦間のモダニズム:1918-1939 煌めきと戸惑いの時代』をきっかけに、当時のドイツ、ベルリンを舞台とした映画作品『さよなら、ベルリン またはファビアンの選択について』をご紹介します。
展覧会『両大戦間のモダニズム 1918-1939 煌めきと戸惑いの時代』について
町田市立国際版画美術館にて開催中の展覧会『両大戦間のモダニズム 1918-1939 煌めきと戸惑いの時代』は、雑誌挿画を含む版画作品で構成することで当時のフランス、アメリカ、ドイツ、ロシア、そして日本など各国文化状況を比較可能な形で展示するとても面白いものでした。
とりわけ国境を接するフランスとドイツの対比は印象的で、展覧会のタイトルにある「煌(きら)めき」がフランスを指すものとすれば、「戸惑い」はドイツを連想する言葉として受け取れるものでしょう。第一次世界大戦では両国とも大きな犠牲を払いましたが、勝利国であるフランスと敗戦国であるドイツでは、その後の社会や文化への影響が大きく異なったという点を強調する意図があるはずです。
もちろんフランスにおいても、ルイ=フェルディナン・セリーヌの長編小説『夜の果てへの旅』のように、第一次大戦の暗い出来事に多大な影響を受けた表現は存在していますが、ファッション雑誌の美しいポショワール(ステンシルで製作された版画)などが取り上げられたフランスのパートと、マックス・ベックマンなどの戦争や都市の不安に触れるような作品が紹介されているドイツのパートとの鮮やかな対比は展覧会のハイライトのひとつとして挙げられるのではないでしょうか。
映画『さよなら、ベルリン またはファビアンの選択について』
展覧会で紹介されている両大戦間のドイツの文化状況の理解について、ドミニク・グラフ監督による映画『さよなら、ベルリン またはファビアンの選択について』(2021)はその格好のガイドとして挙げられるのではないでしょうか。
日本でも児童向けの小説でよく知られるエーリッヒ・ケストナーの「唯一の大人向け」長編小説を原作とする映画『さよなら、ベルリン またはファビアンの選択について』は、1931年のベルリンを舞台に、第一次世界大戦後の混乱と経済危機、文化の退廃、そしてナチスの台頭の時代を、それらに翻弄される青年ファビアンの姿を通して描いた作品です。
ファビアンを演じたのは日本でも話題になった『コーヒーをめぐる冒険』(2013)で主演をつとめたトム・シリング。ヌーヴェル・ヴァーグを代表する俳優ジャン=ピエール・レオを想起するような、その記名性の高い演技が現代のベルリンを舞台にした『コーヒーをめぐる冒険』と1931年のベルリンを描いた『さよなら、ベルリン』をはからずもつないでいるようでもあります。
大戦間の時代と現代をつなげる表現
トム・シリングという個性が映画を跨ぎ、過去と現在のドイツを結びつける一方、『さよなら、ベルリン』自体も当時のアーカイブ映像と現代のドイツで撮影された劇映画の場面をつなぐことで独特な映像表現を成立させています。
それは1931年についての突飛でグロテスクなモンタージュを施した時代劇でありつつも、ドミニク・グラフ監督自身も言及する現代ドイツとワイマール時代の類似性を意識した現代劇としても見ることができるものです。
・
展覧会『両大戦間のモダニズム:1918-1939 煌めきと戸惑いの時代』は町田市立国際版画美術館にて12/1まで開催されています。映画『さよなら、ベルリン またはファビアンの選択について』はプライムビデオなど配信プラットフォームで視聴可能です。
展覧会で出会う版画作品と、映画の中でファビアンが目にする世界。過去と現在の重なりにも思いを馳せながら、展示と映画を跨いで味わってみてはいかがでしょうか。(了)
