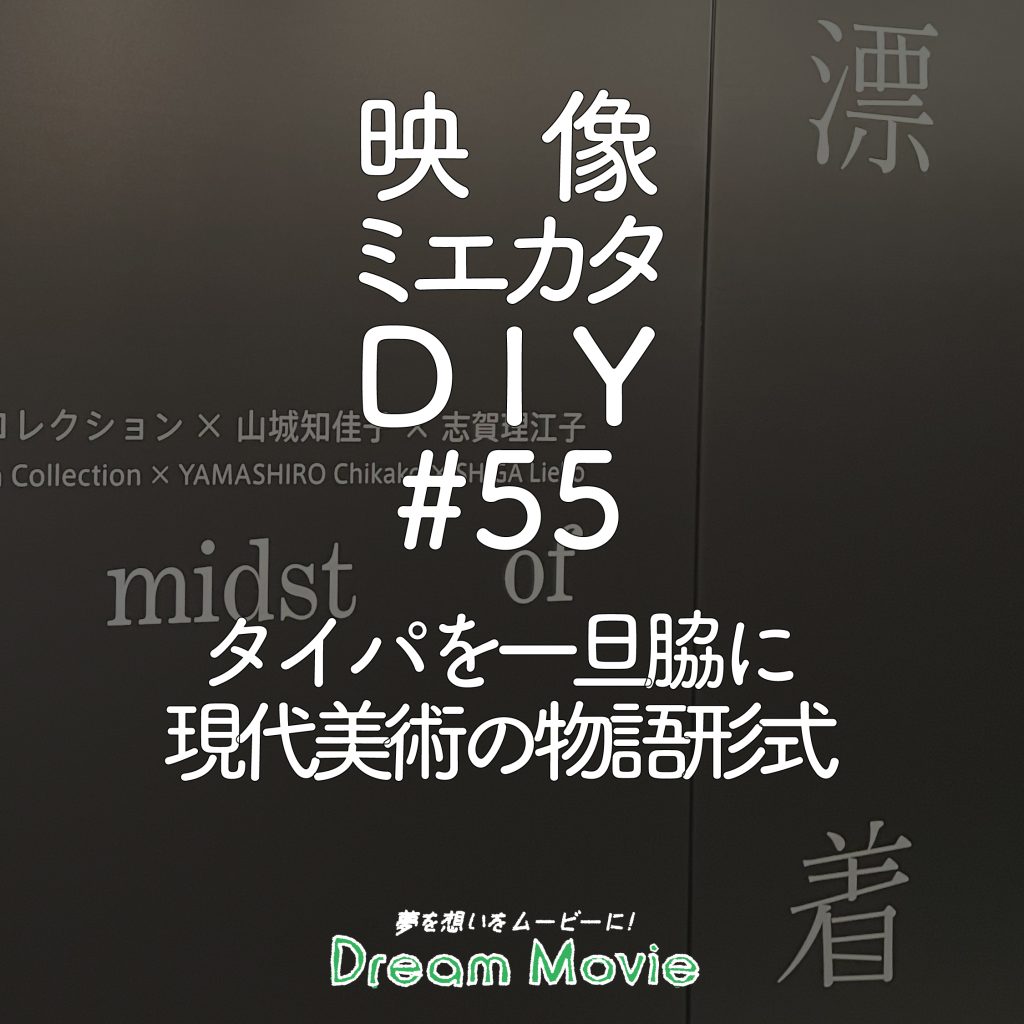 「映像ミエカタDIY」は、当たり前のように受け取っている映像の効果について、身近な素材を取り上げながら改めてその面白さを確認していくシリーズです。今回は現在アーティゾン美術館で開催中の展覧会『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山城知佳子×志賀理江子 漂着』についてご紹介します。
「映像ミエカタDIY」は、当たり前のように受け取っている映像の効果について、身近な素材を取り上げながら改めてその面白さを確認していくシリーズです。今回は現在アーティゾン美術館で開催中の展覧会『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山城知佳子×志賀理江子 漂着』についてご紹介します。
動画コンテンツに慣れ親しんいる人々にとって、いまでは「物語」や「物語る」ことにさえ、効率よく理解でき、時間対効果(タイパ)が高いことが求められる傾向があります。YouTubeを開けば、どんな複雑なテーマも数分で要約され、答えが提示されます。そこでは物語は即座に消化できる「コンテンツ」であり、”わかる”ことが鑑賞の前提とされています。
しかし、先日足を運んだ展覧会『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山城知佳子×志賀理江子 漂着』で感じたのは、「タイパ」や「わかりやすさ」の真逆にある、「わからなさ」の力でした。
それぞれの作家によるインスタレーションは、山城さんの場合は沖縄、志賀さんの場合は宮城石巻について、土地とその記憶が結ぶ物語を扱うものでした。その手に負えないぐらいの濃密さを前にかなり長い時間、会場を歩きまわることになりました。
それぞれの作家にはそれぞれの物語の”きっかけ”があり、それが独自の形式へと結びついています。そういったもの目の前にしたときに気づくのは、私たちが普段いかに安定した形式の物語を前にして「内容を理解する」ことにフォーカスしているかということです。そういったものと比較すると現代美術はまるで、形式と内容を簡単に分割できないような作品の独自性によって”わからなさ”のレッスンをしているかのようです。
志賀さんのインスタレーション《なぬもかぬも》は、巨大な「写真絵巻」のようであり、それ自体が展示空間を仕切る壁のように存在しています。そこに記された莫大な量のテキストと生々しいイメージ、空間を包み込む音響(カエルの声?)を前にした時の途方もなさ。山城さんの複数の映像や音声を用いたインスタレーション《Recalling(s)》は、明確な一本のストーリーラインを提供しません。過去の記憶、異なる場所の歴史、そして祈りのような「声」が重なり合ったり衝突したりする様は、より直接的な”わからなさ”へのアプローチとしても考えられるのかもしれません。
わかろうと必死に頭をフル回転させ、それでも容易にわかることがないものを目の前にする。それは展示会場でのすごく特別な経験であると同時に、とても日常的な経験に近いものであることにも気がつきます。目の前の人とわかりあうことの難しさ、どうしたらあなたを「わかった」と言えるのか。本来日常にはそのような当たり前の「わからなさ」が溢れているはずです。
・
『ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山城知佳子×志賀理江子 漂着』展は東京・八重洲にあるアーティゾン美術館で2026年1月12日まで開催中です。作家それぞれの形式で立ち上がる物語を前に圧倒されることで、ついでに自分の日常にある「わからなさ」と改めて向かい合う。ぜひ展覧会に足を運んでみてはいかがでしょうか。
(了)
