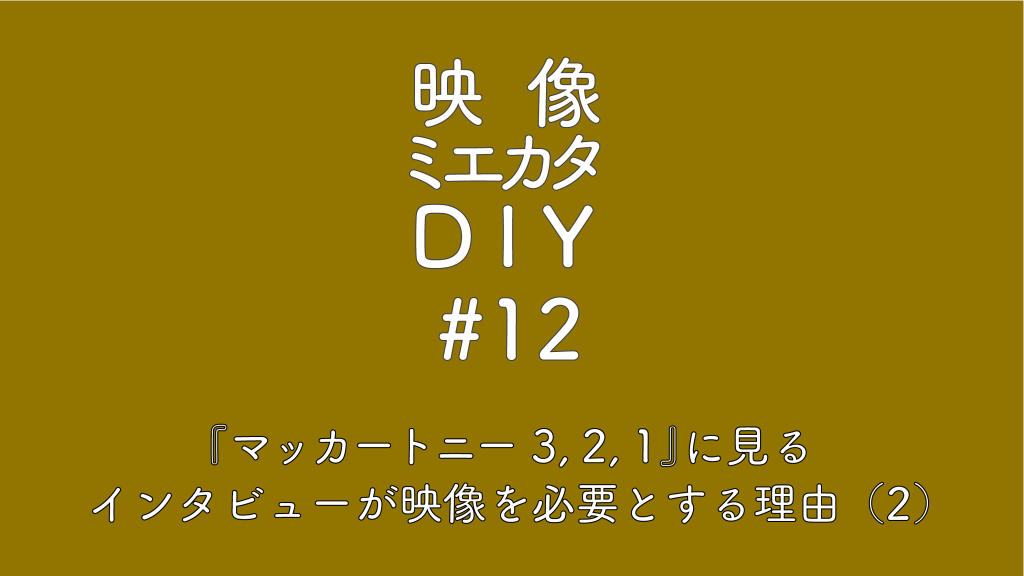
「映像のミエカタDIY」は、当たり前のものとして受け取っている映像の効果について、身近な素材を取り上げながら、改めてその面白さを確認していくシリーズです。
今回も前回に引き続き「『マッカートニー 3, 2, 1』に見る、インタビューが映像を必要とする理由」と題して、インタビューの映像表現について、ポール・マッカートニーが自身の音楽キャリアを振り返るインタビュー映像で構成された非常に優れたドキュメンタリー・シリーズに触れながら考えていきます。
前回では、「インタビューを映像で表現すること」の優位性」についての話題から、『マッカートニー 3, 2, 1』には「語りが生まれる瞬間を記録する」という映像表現におけるインタビューの醍醐味が多分に含まれているというお話をしました。今回は作品のそういった演出の特徴について具体的に紹介していきます。
1.語りのきっかけとしての「聴く/聞こえる」
『マッカートニー 3, 2, 1』では、聞き手である音楽プロデューサーのリック・ルーベンが質問をして、それにポール・マッカートニーが応えていくという基本的な流れを、様々な演出で補強しています。
その一つは、質問に直接的に結びついている楽曲をインタビューの中で出演する二人が実際に再生して聴くということです。それはポールが自身の制作した楽曲のディテールを思い出す、新たに発見するといった作業を促していく役割を担っています。
インタビューにおける話題の中心を言葉や視覚だけではなく、実際にその場で再生した楽曲を聴くことによってフォローし続けるのは、インタビュー当事者だけではなく、視聴者の話題に対する没入を考える上でも効果の高い演出になっています。
この「聴く」という演出については、映像におけるBGMの使用という側面から考えても興味深いところです。現代の劇映画では、劇中で使用される音楽/BGMについては、「劇中で実際に登場人物たちにも聞こえている/聴いている(登場人物がレコードを再生する、移動中に車内で音楽を聴く、劇中の店内で流れている)もの」=「観客が聴いているもの」という考え方による演出が当たり前のものになっています。その劇映画の感覚をインタビューに持ち込んでいることは、注目すべき点だと思います。
2.聞き手の役割を映し出す
インタビューにおける聞き手に必要な資質の一つには、話し手とそこで生じる話題についての造詣の深さが挙げられるでしょう。その点については、英米のポップミュージック史に残るような録音物の制作に携わってきたリック・ルーベンは適役です。
プロデューサーという立場からの質問は、音楽雑誌等のインタビュー(音楽の書き手が聞き手を務める)とは趣の異なるもので、各楽曲の具体的なプロダクションについての話題は、実際に音源を聴くという行為と併せてコンテンツに独自性を与えています。インタビューで取り上げられた楽曲がリック・ルーベンによる選択であることを考えても、聞き手がインタビューにおいてとても重要な存在であることを改めて認識させてくれます。
実際の映像上でもそういった聞き手の役割、重要性を伝えるような演出意図を感じ取ることができます。
通常のインタビューでは中心的な被写体に話し手が設定されます。『マッカートニー 3, 2, 1』の場合でも、タイトルの通り中心的な被写体はもちろんポールであることは明白ですが、聞き手であるリック・ルーベンを出来る限り画面に収め続けようという意図を強く感じます。それは、ポールの語りのタイミングでそれに耳を傾けるリック・ルーベンのワンショットのカットが多用されていることからも明らかです。
劇映画の会話シーンにおいて「聞き手」を映すことの意味については、以前の映像ミエカタDIYでジム・ジャームッシュの作品について紹介した際に触れましたが、この作品においても同様の意図を感じることができます。
つまり、話者中心ではなく「誰がどのように聞いているのか」を重視する態度の表明です。そこでは、会話が複数の人間の存在によって作り出されるものであることや、自明であるが故に、省かれてきた聞き手の存在が改めて強調されることになります。
本作ではそのような聞き手のワンショットが、「語りの生まれる瞬間」を記録するべく遠目から見守るような構図の2ショットの後に続くことにより、聞き手の役割と資質の重要性が強調されることになります。
3.インタビュー内で行われる「協働」
直前に触れた「語りの生まれる瞬間」を待ち構える「遠目から見守るような構図の2ショット」は、インタビューの極めて重要な演出を映し出す大切な役割も担っています。それは聞き手と話し手による「協働」です。作品中の2ショットの大部分において取り上げられているのは、インタビューにおける互いの役割の違いを越えて、二人が協働する姿です。
それは先の話題で触れた「楽曲を再生し、聴く」という作業です。二人は楽曲を実際に流し、ただ聴くのではなく、卓上の大型のコンソールのつまみを操作して、その楽曲の取り上げるべき具体的なパートを絞り込む(同時に鳴っているボーカルや各種楽器の音を、取捨選択する)といった実作業を通して耳を傾け、対話を膨らませていきます。
例えば、「ペニーレーン」におけるピッコロ・トランペットのパートの高音は本来なら出せないような高音を、自分(ポール)の思いついたメロディを再現するために奏者に無理なリクエストをしたというエピソードが、実際の音源から該当楽器の音色を絞り込む作業を二人で行いながら披露されます。
向かい合い座って話すよりも、歩きながら二人で同じ方向に視線を向けている状態の方が「会話が弾む」といったことは、誰にも心当たりのある経験ではないでしょうか。
そういった「語りの生まれる瞬間」についての普遍的な感覚を、音楽的な協働という形で演出に組み込むということ。立ち姿でコンソールをいじり、肩を揺らし熱心に楽曲に聞き入る二人の姿を丁寧に記録してその瞬間を待つという演出が、インタビューで構成された『マッカートニー 3, 2, 1』がドキュメンタリーとして成立するための重要な鍵となっているのではないでしょうか。
・
今回ご紹介した『マッカートニー 3, 2, 1』の具体的な演出は、素晴らしい楽曲の存在をベースにしたものではありますが、「聞き手」や「協働」といった要素はインタビューの映像表現一般においても、取り組むべきところだと感じています。
お読みいただいた皆さまの映像の取り組みの参考になりますと幸いです。(了)
*『マッカトニー 3, 2, 1』について
ポール・マッカートニーがザ・ビートルズでの活動やその後のソロ活動も含めてキャリアを振り返る6つのエピソードで構成されたドキュメンタリー・シリーズ。聞き手に伝説的な音楽プロデューサー、リック・ルービンを迎え、全編で一対一のインタビューの形式が用いられている。2021年7月に米Huluで配信にて公開、日本国内では2021年12月にディズニープラスによる独占配信開始)。
